【深層考察】登山装備の進化史(前編)|わらじから化学繊維革命まで
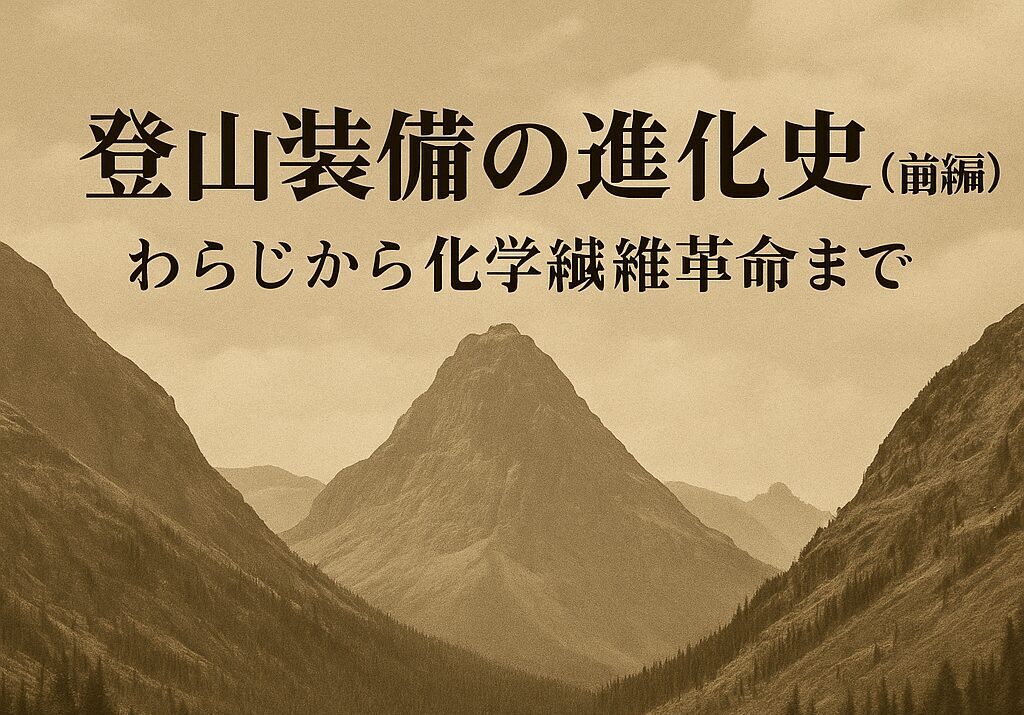
現代の登山者は、ゴアテックスのレインウェア、ビブラムソールの登山靴、超軽量カーボンフレームのザックを身につけて山に登る。しかし、100年前の登山家たちは、重い革靴、綿のシャツ、木製のピッケルで8,000m峰に挑んでいた。
装備の進化は、登山の歴史そのものだ。
不可能とされた山が登られるようになったのは、人間の勇気だけではない。素材革命、技術革新、そして無数の試行錯誤が、登山という行為を根本から変えてきたのである。
わらじで富士山に登った江戸時代の庶民から、ゴアテックスを纏う現代の登山者まで。前編では、古代から平成初期までの装備進化を追う。
【記事情報】
- 難易度: 初級〜中級
- 対象: 登山装備に興味がある人、登山歴史ファン
- 記事タイプ: 装備史・技術解説(前編)
- 文字数: 約6,500字
- キーワード: 登山装備、登山靴、わらじ、ゴアテックス、進化
古代〜江戸時代:自然素材の時代
わらじと草鞋での登山
江戸時代、富士講の庶民たちはわらじ(草鞋)で富士山に登っていた。現代の感覚では信じられないが、当時の日本人にとって、わらじは最も一般的な履物だったのである。
わらじの利点は、意外にも多い。
わらじの特徴:
- 軽量性:片足わずか50g程度
- フィット性:足に巻きつけるため密着度が高い
- グリップ:濡れた岩でも意外と滑りにくい
- 修理可能:現地で編み直せる
- 安価:誰でも手に入る
しかし、欠点も明白だった。
わらじの欠点:
- 耐久性:1日で履きつぶす
- 防水性:皆無
- 保温性:ほとんどない
- 怪我のリスク:石や岩で簡単に傷つく
それでも、庶民にとってわらじ以外の選択肢はなかった。富士講の記録には、「草鞋を3足持参すべし」という記述が頻繁に見られる。登山中に何度も履き替える前提だったのだ。
修験者の装備
一方、修験道の山伏たちは、より実践的な装備を持っていた。
履物:
- 皮製の足半(あしなか):つま先だけを覆う簡易的な履物
- 脚絆(きゃはん):脛を保護する布
- 場合によっては裸足
衣類:
- 麻や木綿の白装束
- 袈裟(けさ)
- 頭襟(ときん):額当て
道具:
- 金剛杖(こんごうづえ):現代のトレッキングポールの原型
- 錫杖(しゃくじょう):音で熊を威嚇
- 法螺貝(ほらがい):仲間との連絡手段
これらの装備は、宗教的な意味合いが強いものの、実用性も兼ね備えていた。特に金剛杖は、体重を支え、バランスを取り、危険を察知する多機能な道具として、現代のトレッキングポールの先祖と言える。
江戸時代の富士講装備
富士講の登山者たちの標準装備は、以下のようなものだった。

基本装備:
- 白装束(死装束の意味も含む)
- わらじ3足
- 金剛杖
- 手甲・脚絆
- 菅笠(すげがさ)
携行品:
- 弁当(握り飯)
- 水筒(竹製)
- 手拭い
- 銭
重量:全体でせいぜい3〜5kg程度
現代の日帰り登山装備と比べると、驚くほど軽量だ。しかし、防寒性や防水性はほぼゼロ。天候が荒れれば、命に関わる状況になったのである。
明治〜大正:近代装備の導入
革製登山靴の登場
明治時代、西洋の近代登山が日本に紹介されると、革製の登山靴が輸入され始めた。
1894年、ウォルター・ウェストンが日本アルプスを登った際、彼が履いていたのはヨーロッパ製の革製登山靴だった。これを見た日本人登山家たちは衝撃を受けたという。
初期の革製登山靴の特徴:
- 素材:牛革、馬革
- 重量:片足800g〜1,200g(わらじの約20倍)
- ソール:革底、後に釘打ち底
- 防水:蜜蝋や油で処理
当初、日本の登山家の多くは「重すぎる」と敬遠した。実際、1,000m級の山を登るには、わらじの方が軽快だったのである。
しかし、岩場や雪渓では革靴の優位性が明白だった。
革製登山靴の利点:
- 足の保護:岩角から足を守る
- アイゼン装着:冬山登山が可能に
- 耐久性:適切な手入れで数年使える
- 安定性:重い荷物でも足元がしっかり
大正時代には、日本でも革製登山靴の生産が始まり、徐々に普及していった。
ウール素材の衣類
明治以前、登山の衣類は麻や木綿が中心だった。しかし、これらの素材には致命的な欠点があった。
綿・麻の欠点:
- 濡れると乾かない
- 保温性が極端に低下
- 重くなる
- 凍結する
西洋から導入されたウールは、革命的だった。
ウールの利点:
- 濡れても保温性を維持(60%程度)
- 吸湿性が高い
- 防臭効果
- 難燃性
大正時代の登山家たちは、ウールのシャツ、ニッカーボッカー、セーターを着用するようになった。これにより、高所での行動が格段に安全になったのである。
特に、1920年代の日本アルプスでは、「ウールのニッカーボッカーに革製登山靴」というスタイルが標準装備となった。
木製ピッケルとザイル
ピッケル(氷斧)は、もともとアルプスの氷河歩行用に開発された道具だ。
明治〜大正期のピッケルは、以下のような構造だった。
木製ピッケルの仕様:
- シャフト:トネリコ材などの硬木
- ヘッド:鍛造鉄
- 長さ:90〜120cm(現代より長い)
- 重量:800g〜1,200g
長いシャフトは、杖代わりにも使えた。現代の短いピッケルは、急斜面専用の進化形と言える。
ザイル(ロープ)も、この時代に日本に導入された。
天然繊維ザイルの仕様:
- 素材:麻、マニラ麻
- 太さ:10〜15mm
- 長さ:20〜30m
- 重量:3〜5kg
天然繊維のザイルは、濡れると重くなり、凍結すると硬直する問題があった。しかし、岩場や雪渓での安全性は飛躍的に向上した。
昭和前期:戦前の装備革命
日本独自の登山靴開発
昭和初期、日本の登山靴メーカーが独自の開発を始めた。
「地下足袋型登山靴」の誕生:
日本の岩場には、ヨーロッパ型の重い革靴より、柔軟性のある履物が適していると考えられた。そこで開発されたのが、地下足袋をベースにした登山靴だ。
地下足袋型登山靴の特徴:
- つま先が分かれた(足袋構造)
- ソール:ゴム底(滑りにくい)
- 重量:片足300g程度(革靴の1/3)
- 利点:岩場でのグリップ力、軽快さ
この「地下足袋登山靴」は、日本の岩場で威力を発揮した。特に沢登りでは、濡れた岩でのグリップ性能が高く評価された。
しかし、欠点もあった:
- 耐久性が低い
- 冬山には不向き
- 重い荷物を背負うには不安定
結局、ヨーロッパ型の革製登山靴が主流となっていくが、地下足袋型の発想は、後の「フェルト底」「ラバーソール」に受け継がれていく。
ナイロンの登場
1938年、デュポン社がナイロンを発明した。これは登山装備史における革命だった。
ナイロンの特性:
- 強度:天然繊維の数倍
- 軽量:同じ強度なら半分以下
- 耐水性:ほぼ吸水しない
- 耐腐食性:カビや腐敗に強い
第二次世界大戦後、ナイロンは民生用に転用され、登山装備に革命をもたらす。
ナイロンザイル:
- 麻ザイルの半分の重量
- 濡れても性能が落ちない
- 伸縮性があり、墜落の衝撃を吸収
ただし、初期のナイロンザイルには「岩角での切断」という致命的な欠点があった。1955年の「ナイロンザイル事件」(前穂高岳での墜落死亡事故)は、装備の安全性を問う契機となった。
この事件をきっかけに、ナイロンザイルの改良が進み、現代の安全なクライミングロープへと進化していく。
軽量化への挑戦
昭和10年代、日本の登山家たちは「軽量化」を追求し始めた。
背景:
- 長期縦走の増加
- 無補給での登山
- より困難なルートへの挑戦
軽量化の工夫:
- ザックの簡素化(装飾を削ぎ落とす)
- テントの小型化(1〜2人用)
- 食料の厳選(カロリー効率重視)
- 装備の多目的化(1つで複数の用途)
この思想は、現代の「ウルトラライト」に通じるものだ。戦前の登山家たちは、すでに「必要最小限の装備で山に挑む」哲学を持っていたのである。
昭和後期〜平成:素材革命の時代
ゴアテックスの衝撃
1969年、アメリカのゴア社がゴアテックスを開発した。これは登山装備史において、最大級の技術革新と言える。
ゴアテックスとは:
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の微多孔質膜
- 1平方インチに90億個の微細な穴
- 水滴は通さないが、水蒸気は通す
革命的だった理由:
それまでのレインウェアは、「防水」か「透湿」のどちらか一方しか実現できなかった。
- ゴム引き雨具:完全防水だが、内側が蒸れる
- 綿のヤッケ:透湿性はあるが、防水性が低い
ゴアテックスは、この矛盾を解決した。
性能:
- 耐水圧:20,000mm以上(バケツの水を余裕で防ぐ)
- 透湿度:13,500g/㎡/24h(汗の水蒸気を外に逃がす)
1970年代後半、ゴアテックス製レインウェアが登山界に登場すると、瞬く間に普及した。それまで「雨の日は山に登らない」が常識だったが、ゴアテックスによって雨天登山が現実的になったのである。
ただし、初期のゴアテックスは高価だった。1着5万円以上という価格は、当時の大卒初任給の半分近い金額だった。
アルミフレームザックの進化
1970年代、ザック(バックパック)も大きく進化した。
外部フレームザックから内部フレームへ:
1960年代までの主流は、外部フレーム型だった。
外部フレーム型の特徴:
- アルミパイプのフレームが外側に露出
- 高重心で長距離歩行に有利
- しかし、岩場では引っかかる
- 見た目がゴツい
1970年代、内部フレーム型が登場した。
内部フレーム型の利点:
- フレームを生地の内側に配置
- 背中にフィットし、重心が安定
- 岩場でも引っかからない
- スマートな外観
この変革により、「重い荷物を長距離」から「軽快に動く」スタイルへと変化していった。
日本で人気のザックメーカー:
- カリマー(イギリス)
- グレゴリー、オスプレー(アメリカ)
- ミレー(フランス)
- 国産:モンベル、カラファテなど
化学繊維の全盛期
ナイロンに続き、様々な化学繊維が登山ウェアに使われるようになった。
ポリエステル:
- 速乾性が高い
- 軽量
- 保温性(中綿として)
- 吸汗速乾シャツに最適
ポリプロピレン:
- 最軽量の繊維
- 吸水しない(濡れても重くならない)
- アンダーウェアに最適
フリース(ポーラテック):
- 1980年代に登場
- ウールより軽く、速乾性が高い
- 保温性はウール並み
- 洗濯が簡単
これにより、「重くて乾かないウール」から「軽くて速乾のフリース」へと移行した。
1990年代には、ほとんどの登山者がフリースを着用するようになり、ウールは一時期、時代遅れとされた(ただし、近年は天然素材として再評価されている)。
登山靴の進化:革からナイロンへ
1980年代、登山靴にも革命が起きた。
ナイロン製登山靴の登場:
- アッパー:革ではなくナイロン生地
- 重量:革靴の半分(片足400g程度)
- メンテナンス:ほぼ不要
- 価格:革靴より安価
利点:
- 軽量で疲れにくい
- 速乾性が高い
- 初心者でも扱いやすい
欠点:
- 耐久性は革より劣る
- 重登山には不向き
- 修理が困難
現代では、「日帰り・小屋泊はナイロン製」「テント泊・冬山は革製」という使い分けが一般的になっている。
まとめと後編予告
前編のまとめ
わらじで富士山に登った江戸時代から、ゴアテックスが登場した1970年代まで、登山装備は劇的に進化した。
主な変革:
- 履物:わらじ → 革靴 → ナイロン製登山靴
- 衣類:麻・綿 → ウール → 化学繊維
- レインウェア:なし → ゴム引き → ゴアテックス
- ザイル:麻 → ナイロン
- ザック:外部フレーム → 内部フレーム
これらの進化により、登山は「命がけの冒険」から「より安全なアクティビティ」へと変化した。
しかし、装備の進化は止まらない。
後編予告
後編では、以下の内容を解説します:
令和のハイテク装備:
- カーボン・チタン素材の超軽量化
- スマートウォッチ・GPS機器
- LED化したヘッドランプ
- 最新の防水透湿素材
未来の登山装備:
- グラフェン、エアロゲルなどの次世代素材
- AIアシスタント、ARグラス
- 環境配慮型装備
FAQ:
- 昔の装備で今も使えるものは?
- 最新装備を揃えるといくら?
- 軽量化しすぎは危険?
装備進化の哲学:
- 技術と人間の関係
- 「道具に頼りすぎない」ことの重要性
前編で見てきたように、装備の進化は登山を変えた。しかし、最も重要なのは、装備を使う「人間の判断力」であることを、後編では深く掘り下げていく。
参考文献・さらに学びたい方へ
📚 書籍
登山装備史
- 『登山用具の歴史』石川三四郎(山と溪谷社、1987年)
- 『山道具メーカー列伝』山と溪谷社編(山と溪谷社、2015年)
- 『ゴアテックスの秘密』大森義彦(講談社ブルーバックス、2005年)
登山史
- 『日本登山史』日本山岳会編(白水社、1956年)
- 『近代登山の父 ウォルター・ウェストン』青木枝朗(山と溪谷社、1984年)
- 『日本百名山』深田久弥(新潮文庫、1982年)
技術書
- 『山岳装備大全』山と溪谷社編(山と溪谷社、2019年)
- 『軽量登山の教科書』高橋庄太郎(山と溪谷社、2016年)
🌐 公式機関・メーカー
- 日本山岳会(JAC):https://www.jac.or.jp/
- モンベル:https://www.montbell.jp/
- ゴア社(ゴアテックス):https://www.gore-tex.jp/
📰 専門雑誌
- 『山と溪谷』(山と溪谷社、1930年創刊)
- 『岳人』(東京新聞、1946年創刊)
- 『PEAKS』(枻出版社、2009年創刊)
関連記事
- 【深層考察・番外編】登山の歴史|なぜ人は山に登るのか?(本シリーズの導入記事)
- 【番外編】登山装備の進化史(後編)|ハイテク時代と未来展望(次回)
※この記事について
本記事には書籍へのアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。リンクを通じて購入された場合、当サイトに紹介料が入りますが、購入価格への影響はありません。記事内容は文献調査と客観的な分析に基づいています。



