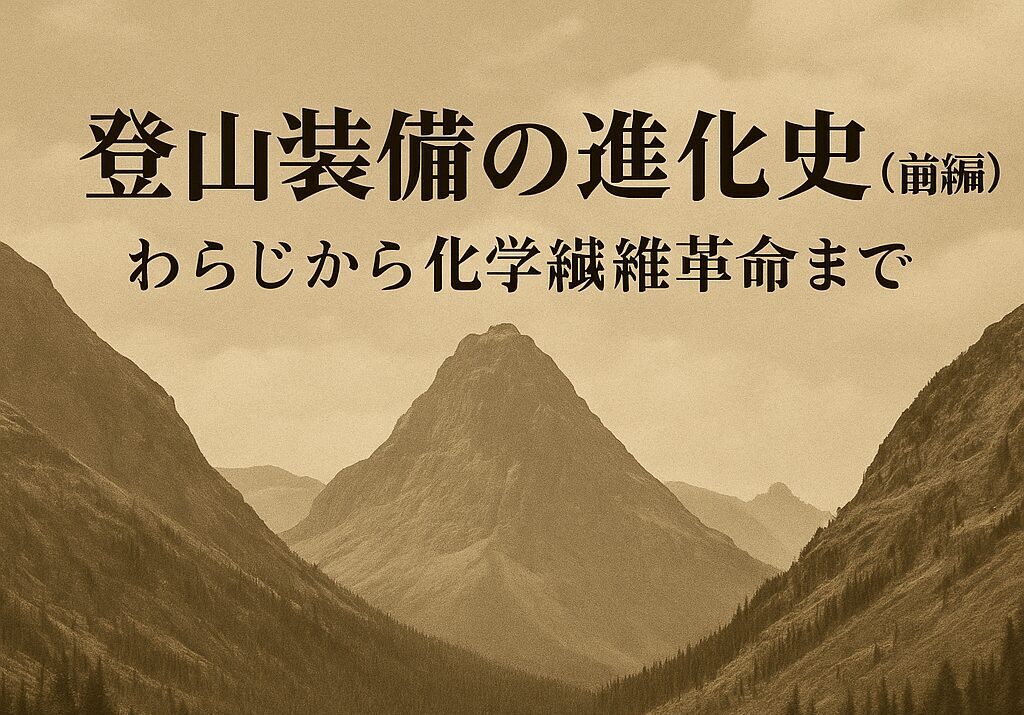【深層考察】なぜ人は山に登るのか?登山7000年の歴史

「そこに山があるから」―登山家ジョージ・マロリーの有名な言葉です。しかし、この一言では語り尽くせないほど、人類と山の関わりは深く、複雑です。
宗教、探検、科学、スポーツ、そして自己実現―。時代によって、地域によって、人が山に登る理由は変化してきました。それは単なる「趣味の歴史」ではなく、人類の精神史、文化史そのものなのです。
この記事では、通常の登山ガイドでは触れられない「登山の本質」に迫ります。古代の山岳信仰から最新の商業登山まで、7000年以上にわたる登山の歴史を深層から考察します。
山に登ったことがない人も、ベテラン登山家も、この歴史を知ることで、「山」という存在の意味が変わるはずです。
目次
古代〜中世:神々の住む場所としての山
山岳信仰の始まり―なぜ人は山を崇めたのか
人類にとって、山は長い間「畏怖の対象」でした。高くそびえ立ち、雲に覆われ、時に雷鳴を轟かせる山々は、神々が住む聖域と考えられていました。
古代ギリシャでは、オリンポス山が神々の住処とされ、日本では富士山や白山が信仰の対象となりました。中国の五岳(泰山、華山、衡山、恒山、嵩山)も、古くから神聖視されてきました。

この時代の「登山」は、宗教的な巡礼や修行の一環として行われていました。山頂に到達することそのものが目的ではなく、神に近づき、悟りを開くための手段だったのです。
日本の修験道
日本独自の山岳信仰として発展したのが「修験道」です。7世紀頃、役小角(えんのおづぬ)が開祖とされ、山中での厳しい修行を通じて超自然的な力を得ることを目指しました。
修験者(山伏)たちは、険しい山道を歩き、滝に打たれ、断食を行いながら、山の霊力を身につけようとしました。彼らにとって、登山は肉体的な挑戦であると同時に、精神的な修行でもあったのです。
富士山、立山、白山、大峰山などは、修験道の聖地として、多くの修験者が訪れました。現代の登山道の多くは、実はこの修験者たちが切り開いた道を基にしています。
ヨーロッパの山岳観
一方、中世ヨーロッパでは、山は「危険で不毛な場所」と見なされていました。アルプスの高い峰々は、悪魔や怪物が住む恐ろしい場所と考えられ、できるだけ避けるべき対象でした。

ただし例外もあります。1336年、イタリアの詩人ペトラルカがヴァントゥー山(標高1,912m)に登頂したという記録が残っています。彼は純粋に「景色を見たい」という動機で登ったとされ、これは近代登山の萌芽とも言えるエピソードです。
しかし、本格的な登山文化がヨーロッパで花開くには、さらに数百年の時間が必要でした。
近代登山の夜明け:18〜19世紀
アルプス登山の始まり
18世紀後半、ヨーロッパで科学的探究心が高まる中、山への見方が変わり始めます。スイスの博物学者オラス=ベネディクト・ド・ソシュールは、アルプスの氷河や地質に関心を持ち、1760年にモンブラン初登頂への懸賞金をかけました。
そして1786年8月8日、地元シャモニーの医師ミシェル・パカールと水晶採掘人ジャック・バルマが、ヨーロッパ最高峰モンブラン(標高4,808m)の初登頂に成功しました。これは近代登山史における記念すべき瞬間となりました。
この成功をきっかけに、アルプスの高峰への挑戦が次々と行われるようになります。登山は、宗教的行為から「スポーツ」「科学探究」へと性質を変えていったのです。
黄金時代:アルプスの初登頂ラッシュ
19世紀中頃は「アルプス登山の黄金時代」と呼ばれます。1857年にイギリスでアルパイン・クラブ(世界初の登山クラブ)が設立されると、アルプスの未踏峰への挑戦が加速しました。
【コラム】マッターホルンの悲劇
1865年7月14日、エドワード・ウィンパー率いるチームが、「登れない山」とされていたマッターホルン(4,478m)の初登頂に成功しました。しかし、下山中にロープが切れ、4名が滑落死する大惨事が発生。この事故は世界中に衝撃を与え、登山の危険性とリスク管理の重要性を世に知らしめる出来事となりました。
この悲劇は、登山が単なる「冒険」ではなく、命をかけた挑戦であることを示したのです。
この時代、登山は主にヨーロッパの富裕層の娯楽でした。登山家たちは地元のガイドを雇い、時には数週間かけて山に挑みました。登山用具も発達し、ピッケル、アイゼン、ザイルなどが使われるようになります。
登山技術の進化
19世紀後半から20世紀初頭にかけて、登山技術は大きく進歩しました。
ロッククライミング技術の発達により、それまで不可能とされていた岩壁の登攀が可能になりました。ドイツやオーストリアの登山家たちが、より困難なルートに挑戦し始めます。
冬季登山も始まりました。1874年、イギリスの登山家たちが真冬のモンブラン登頂に成功し、季節を問わず山に登る文化が生まれました。
また、高所登山への関心も高まります。ヒマラヤやアンデスの高峰への探検が始まり、人類は「8,000m峰」という新たな挑戦に直面することになります。
日本の近代登山史
江戸時代:庶民の登山文化
日本では、江戸時代に独特の登山文化が花開きました。それが「富士講」です。
富士講は、富士山信仰を基にした庶民の信仰組織で、講を組んで富士山に登拝しました。江戸時代後期には江戸だけで数百の富士講があり、毎年夏になると多くの人々が富士山を目指しました。

これは世界的に見ても珍しい、「大衆による登山」の文化でした。ヨーロッパの登山が貴族や富裕層の特権だった時代に、日本では庶民が山に登っていたのです。
明治時代:近代登山の導入
明治時代になると、西洋の近代登山が日本に紹介されます。
1894年、イギリス人宣教師ウォルター・ウェストンが来日し、日本アルプスの山々を登りました。彼の著書『日本アルプス 登山と探検』は、日本の山岳の美しさを世界に紹介し、日本人にも「スポーツとしての登山」という概念をもたらしました。

1905年には日本初の登山クラブ「日本山岳会」が設立されます。これ以降、科学的・スポーツ的な登山が日本でも本格化していきます。
戦前の登山ブーム
大正から昭和初期にかけて、日本では登山ブームが起こりました。
鉄道網の整備により、都市部から山岳地帯へのアクセスが容易になったことが大きな要因です。「山の日」の休暇を利用して、サラリーマンや学生が山に登るようになりました。
1930年代には、多くの登山雑誌が創刊され、山小屋も整備されていきます。槍ヶ岳、穂高岳、剱岳などの北アルプスの名峰が、登山者たちの憧れの的となりました。
また、この時期には女性登山家も活躍し始めます。1920年代に入ると、女性だけの登山隊も編成されるようになりました。
8,000m峰への挑戦:戦後の登山史
エベレスト初登頂
第二次世界大戦後、登山界の最大の目標は「世界最高峰エベレスト(標高8,848m)の初登頂」でした。
1920年代から何度も挑戦が行われましたが、高所の過酷な環境、酸素不足、極寒という三重苦に阻まれ、多くの登山家が命を落としました。
そして1953年5月29日、イギリス隊のエドモンド・ヒラリーとシェルパのテンジン・ノルゲイが、ついにエベレスト登頂に成功します。これは人類史における偉業として、世界中で祝福されました。

Jamling Tenzing Norgay – http://www.tenzing-norgay-trekking.de, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11252058による
8,000m峰14座の完登競争
エベレスト登頂後、世界には8,000mを超える山が14座あることが知られており、それらすべてに登ることが新たな目標となりました。
1950年、フランス隊がアンナプルナ(8,091m)に初登頂したのを皮切りに、次々と8,000m峰が登られていきます。
- K2(8,611m):1954年 イタリア隊
- カンチェンジュンガ(8,586m):1955年 イギリス隊
- マカルー(8,485m):1955年 フランス隊
- マナスル(8,163m):1956年 日本隊
特筆すべきは、1956年の日本隊によるマナスル初登頂です。これは日本登山界にとって歴史的快挙であり、戦後の日本人に大きな勇気を与えました。
そして1986年、イタリアの登山家ラインホルト・メスナーが、世界で初めて8,000m峰14座すべての登頂に成功しました。
新しい挑戦:無酸素登頂と単独登頂
8,000m峰がすべて登られた後、登山家たちは新たな挑戦を求めました。
無酸素登頂:1978年、メスナーとペーター・ハーベラーが、酸素ボンベを使わずにエベレスト登頂に成功しました。これは「人間の限界」への挑戦でした。
単独登頂:1980年、メスナーがエベレストを単独・無酸素で登頂。究極の孤独と危険に立ち向かう姿は、多くの人々を魅了しました。
冬季登頂:より過酷な条件下での登山も行われるようになり、8,000m峰の冬季登頂が次々と達成されていきます。
現代の登山:多様化と大衆化
商業登山の発達
1980年代以降、登山は大きく様変わりしました。それが「商業登山」の発達です。
登山ガイド会社が、高額な料金で一般人をエベレストに連れて行くサービスを始めました。経験豊富なガイド、シェルパのサポート、酸素ボンベなどのサポートにより、以前は限られたエリート登山家しか挑戦できなかった8,000m峰に、一般人も登れるようになったのです。
しかし、これは環境問題や遭難事故の増加という新たな課題も生み出しました。1996年のエベレスト大量遭難事故(8名死亡)は、商業登山の危険性を世界に知らしめる出来事となりました。
日本の登山ブーム
日本では、1990年代後半から「中高年の登山ブーム」が起こりました。
定年退職後の趣味として、また健康維持のために、50〜70代の人々が山に登り始めたのです。百名山ブーム、山ガール現象など、さまざまな形で登山人口が拡大しました。
登山用品も進化し、軽量で高性能なウェア、GPS機器、軽量テントなどが開発され、より快適で安全な登山が可能になりました。
新しい登山のスタイル
現代の登山は、非常に多様化しています。
- トレイルランニング:山道を走るスポーツとして人気上昇
- ボルダリング・スポーツクライミング:都市部のジムでも楽しめる
- バックカントリースキー:冬山とスキーの融合
- ソロ登山:SNSの発達で情報共有が容易に
- 山岳写真・山岳動画:山の魅力を発信する新しい文化
登山は、もはや「頂上を目指す」だけではなく、山での時間を楽しむ、自然と触れ合う、自分自身と向き合うなど、多様な価値観で楽しまれるようになりました。
まとめ:登山の歴史が教えてくれること
人類の登山の歴史、すなわち山岳史を振り返ると、いくつかの大きな変化が見えてきます。これは単なる「登山文化」の変遷ではなく、人類の探検史であり、冒険史であり、精神史そのものです。
信仰から冒険へ:山は神聖な場所から、人間が挑戦する対象へと変わりました。山岳崇拝から登山思想への転換です。
特権から大衆へ:一部のエリートの娯楽だった登山は、誰もが楽しめるアクティビティになりました。これは山岳文化の民主化とも言えます。
征服から共生へ:山を「征服する」という考え方から、「山と共にある」「自然を守る」という意識へと変化しています。登山哲学の進化です。
しかし、どの時代にも共通しているのは、人間が山に魅了され続けてきたという事実です。
山は私たちに、自然の偉大さ、人間の小ささ、そして同時に人間の可能性を教えてくれます。困難を乗り越えて頂上に立つ達成感、美しい景色、仲間との絆―これらは、どの時代の登山家も感じてきたものです。
「そこに山があるから」登る。この単純でありながら深い言葉は、これからも人類と山の関係を表し続けるでしょう。
あなたも、この長い登山の歴史の一部として、山に登ってみませんか?
よくある質問(FAQ)
Q1. 昔の人は今のような登山靴もなしでどうやって登っていたのですか?
驚くべきことに、修験者たちは「わらじ」で険しい山道を歩いていました。江戸時代の富士講の人々も、草鞋に金剛杖という簡素な装備で富士山に登っていたのです。現代の私たちからすると信じられませんが、彼らは幼い頃から裸足や薄い履物で生活していたため、足の裏が丈夫で、バランス感覚も優れていました。むしろ、過保護な装備に頼らないからこそ、地面を感じ取る能力が研ぎ澄まされていたとも言えます。
Q2. 女性が登山できるようになったのはいつからですか?
実は日本では、明治時代まで多くの霊山が「女人禁制」でした。富士山も1872年(明治5年)までは女性の登山が禁止されていたのです。ヨーロッパでも19世紀は「女性には登山は無理」という偏見が根強く、スカートでの登山を強いられました。しかし1871年、イギリスのルーシー・ウォーカーがマッターホルンに登頂するなど、先駆的な女性たちが偏見を打ち破っていきました。日本でも1920年代には女性登山家が活躍し始め、現代では性別による制限はほぼなくなっています。
Q3. 登山で最も多くの人が亡くなった山はどこですか?
意外かもしれませんが、エベレストではありません。最も死者が多いのはK2(標高8,611m)で、登頂成功率が約65%に対し、死亡率は約25%という「最も危険な8,000m峰」です。日本の山では、滑落事故の多い谷川岳が「魔の山」として知られています。ただし、死者数だけで危険度は測れません。エベレストも商業登山の発達で登山者が激増した結果、累積死者数は300名を超えています。
Q4. 登山ブームで山が汚れているって本当ですか?
残念ながら事実です。特にエベレストでは、登山者が残したゴミ、テント、酸素ボンベ、さらには遺体までもが「世界最高のゴミ捨て場」と呼ばれる状況を作り出しています。日本でも富士山のゴミ問題が深刻化し、2013年に世界遺産登録された際も「ゴミ問題の改善」が条件とされました。近年は各国で清掃活動が行われ、入山料制度やゴミ持ち帰り義務化などの対策が進んでいますが、まだ課題は山積みです。登山の大衆化と環境保護のバランスが問われています。
Q5. 今でも未登頂の山はあるのですか?
はい、実は数多く存在します。中国・ブータン国境のガンケル・プンスム(標高7,570m)は、世界最高峰の未登頂峰です。ブータン政府が宗教的理由で登山を禁止しているため、今後も登られることはないでしょう。また、パキスタンやチベットには政治的・宗教的理由で入山が制限されている未登頂峰が多数あります。技術的に登れる山でも、現地の信仰を尊重して「あえて登らない」という選択をする時代になっているのです。
Q6. エベレストに登るにはいくらかかりますか?
商業登山ツアーを利用する場合、ネパール側からのルートで約500万〜1,000万円、チベット側からは約400万〜600万円が相場です。内訳は、ネパール政府への登山許可料(約130万円)、ガイド・シェルパ費用(約200万〜300万円)、装備費(約100万円)、往復航空券・宿泊費などです。さらに、高所順応のため2ヶ月近く現地に滞在する必要があり、その間の仕事を休む機会費用も考えると、総額1,000万円以上かかることも珍しくありません。つまり、エベレストは今も「金持ちの山」なのです。
Q7. 登山の歴史を学ぶと、登山がもっと楽しくなりますか?
間違いなく楽しくなります。例えば、富士山に登るとき「江戸時代の庶民も同じ道を白装束で登っていたんだ」と想像すると、ただの登山が歴史との対話になります。アルプスで「150年前、マッターホルンでは命をかけた初登頂競争があったんだ」と思えば、景色の見え方が変わるはずです。山は過去から未来へとつながるタイムカプセルです。歴史を知ることで、あなたの登山は単なるスポーツから、人類の物語の一部になるのです。
参考文献・さらに学びたい方へ
この記事は、以下の文献・資料を参考に執筆しました。
📚 書籍
日本の登山史
- 『日本登山史』日本山岳会編(白水社、1956年)
- 『近代登山の父 ウォルター・ウェストン』青木枝朗(山と溪谷社、1984年)
- 『日本百名山』深田久弥(新潮文庫、1982年)
- 『修験道 山岳信仰の歴史と文化』宮家準(講談社学術文庫、1996年)
- 『富士講の歴史』岩科小一郎(名著出版、1983年)
世界の登山史
- 『アルプス登山史』エドワード・ウィンパー著、大久保喜一訳(白水社、1981年)
- 『エベレストを越えて』エドモンド・ヒラリー著、佐藤悦夫訳(朝日新聞社、1955年)
- 『8000メートル峰14座に挑む』ラインホルト・メスナー著(山と溪谷社、1987年)
- 『空へ エベレスト悲劇はなぜ起きたか』ジョン・クラカワー著(文藝春秋、1998年)
登山思想・文化論
- 『山の思想史』丸山康夫(岩波新書、2002年)
- 『登山の哲学』竹内洋岳(NHK出版新書、2014年)
🌐 公式機関・Webサイト
- 日本山岳会(JAC):https://www.jac.or.jp/
- 国際山岳連盟(UIAA):https://www.theuiaa.org/
- ヒマラヤンデータベース:https://www.himalayandatabase.com/
- 富士山世界遺産センター:https://fujisan-whc.jp/
📰 専門雑誌
- 『山と溪谷』(山と溪谷社、1930年創刊)
- 『岳人』(東京新聞、1946年創刊)
- 『岩と雪』(山と溪谷社、1958-1997年)
📊 統計・データ
- 警察庁「山岳遭難統計」
- 気象庁「過去の気象データ」
- ネパール観光省「エベレスト登山統計」
※この記事について
本記事には書籍へのアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。リンクを通じて購入された場合、当サイトに紹介料が入りますが、購入価格への影響はありません。記事内容は文献調査と客観的な分析に基づいています。